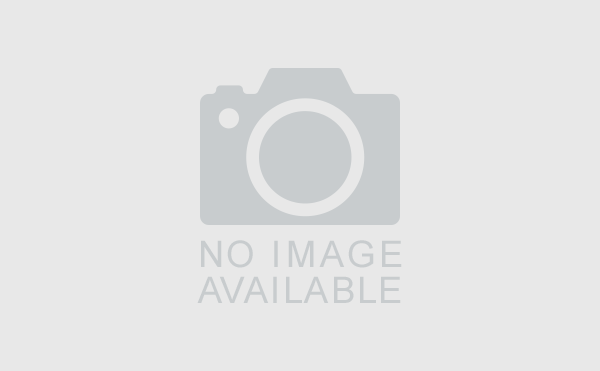駒込武講演会「呉新榮と三つの戦争―台湾・塩分地帯における戦争経験―」
参加申込フォーム
https://forms.gle/aFJpmBxE6Nf4tvM1A
自主講座「認識台湾 RenshiTaiwan」連続セミナー”台湾・継続する植民地戦争”
呉新榮と三つの戦争
―台湾・塩分地帯における戦争経験―
日時:2025年12月4日(木)18時~
場所:京都大学総合研究4号館2階講義室3
講師:駒込武(京都大学教授・自主講座「認識台湾」代表)
台湾の「塩分地帯」とは、台湾西岸の南半部(北は嘉義から南は台南まで)の沿海地域を指す。海に流れ込む河川の砂の影響で河川はしばしば氾濫を起こし、土壌は大量の塩分を含むために農耕に適さず、漁業や養殖、塩づくりなどで生計を立てる人が多かった。
「3つの戦争」とは、日本軍による台湾占領に抗するための郷土防衛戦争(1895年)、日本軍の軍人や軍属として中華民国その他の連合国と戦うことを迫られた戦争(1937年~1945年)、台湾史家呉密察が「砲声はあまり響かないが依然戦争であるような戦争」と呼んだ台湾二・二八事件(1947年)である。
このセミナーでは、台湾のなかでも「辺境」な性格の色濃いこの土地で生まれ育ち、医師、詩人、地方政治家として活躍した呉新榮(1907~1967)の日記を主な手がかりとしながら、この3つの戦争が折り重なる時代を台湾の人びとがどのように生き延びたのかを追う。
呉新榮は、医師、詩人、地方政治家として活躍した人物である。著名な漢詩詩人を父として、1907年に生まれる。公学校、台湾総督府商業専門学校を経て、1928年に東京医学専門学校に入学、共産党一斉検挙(四・一六事件)で検挙されて1ヶ月近く投獄された。
1932年に「塩分地帯」の中心地である佳里に戻って、叔父の「佳里医院」を継承しながら文学活動に参加、台湾文芸連盟佳里支部を立ち上げる。1939年には地方制度改正によりようやく実現された街庄協議会員選挙に出馬し、最高得票で佳里街協議会員に当選した。
自ら「先駆者」を語る若き知識人であり、同時に、地方の名士でもあった。最初の戦争(台湾郷土防衛戦争)について父や祖父からどのようなことを伝え聞いていたのか、2番目の戦争(日中戦争・第二次世界大戦)のさなかに展開された「皇民化政策」にどのような対応したのか、そして、「戦後」であるはずの時代に起きた、「砲声はあまり響かない」戦争のなかでどのような「地獄」を見ることになるのか…。
戦争と言えば「あの戦争」であり、その戦争は1945年をもって終わったと考えがちな日本社会の戦争観を問い直すためにも、3つの戦争をつなげて考えてみたい。